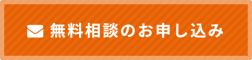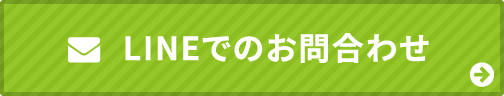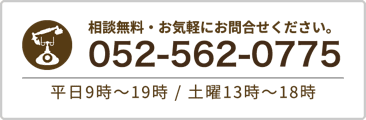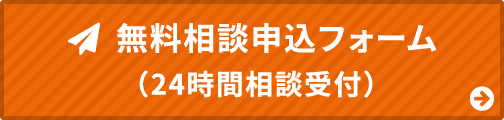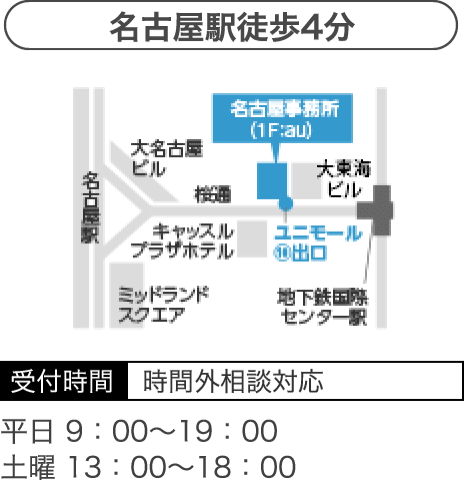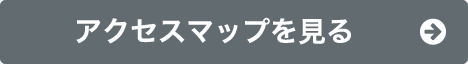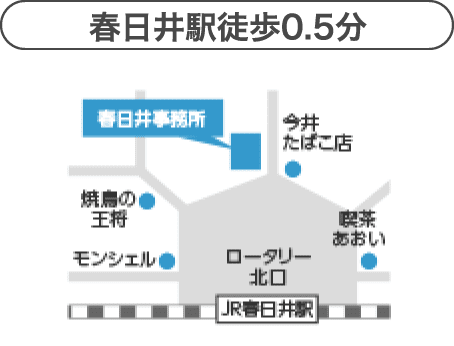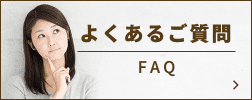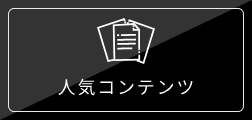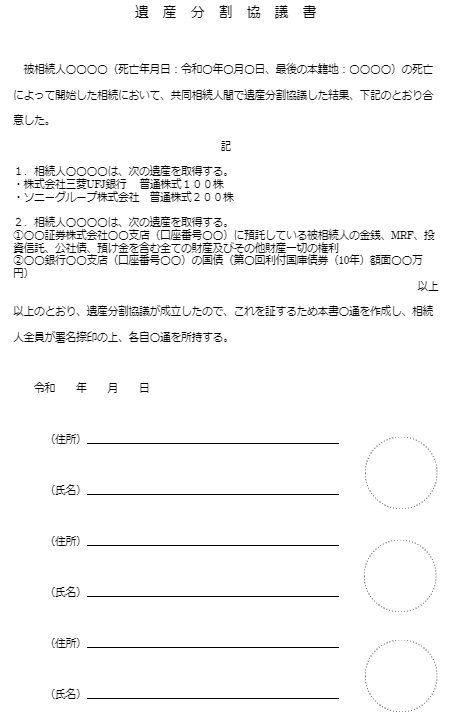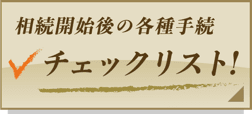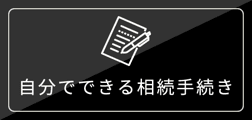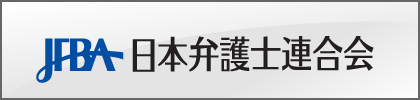遺留分侵害額請求ができるのは、相続があったこと及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間です。この期間を経過すると、相手方が消滅時効を援用した場合、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。
また、このような事情を知らなくても、被相続人が亡くなった日から10年が経過した場合には、遺留分侵害額請求権は消滅します(除斥期間)。
1.遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から一年間経過すると、相手方が消滅時効を援用した場合、時効によって消滅します(民法1048条)。
また、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったか否かにかかわらず、被相続人が亡くなった日から10年が経過した場合には、遺留分侵害額請求権は消滅します(除斥期間)。
これは、受贈者又は受遺者が長期間不安定な法律関係に置かれることを回避するため、短期の消滅時効が定められたものです。
2.消滅時効の起算点
消滅時効の起算点は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」です。
具体的には、被相続人が死亡したことに加え、単に生前贈与や遺贈があったことを知ったことのみならず、当該贈与や遺贈が自己の遺留分を侵害し、侵害額請求の対象となることまで認識したことが必要とされています。
3.遺留分侵害額請求権の消滅時効を中断する方法
遺留分侵害額請求権の消滅時効を中断するには、遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。遺留分侵害額請求権の行使の方法は、特に形式が決まっているわけではなく、相手方に対する意思表示によって行うことで足ります。
ただし、後に時効期間内に遺留分侵害額請求権を行使したことを証明できるようにするため、通常は内容証明郵便(配達証明付)で請求を行います。
4.民法改正の施行日
従前の遺留分減殺請求権は、民法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分侵害額請求権となりました。
遺留分侵害額請求権の対象となるのは、2019年7月1日以降に開始された相続(被相続人の死亡日が同日以降)です。2019年6月30日以前に開始した相続については、改正前の遺留分減殺請求制度の対象となります。もっとも、時効の期間については、改正前後で違いはありません。
参考条文
民法
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。