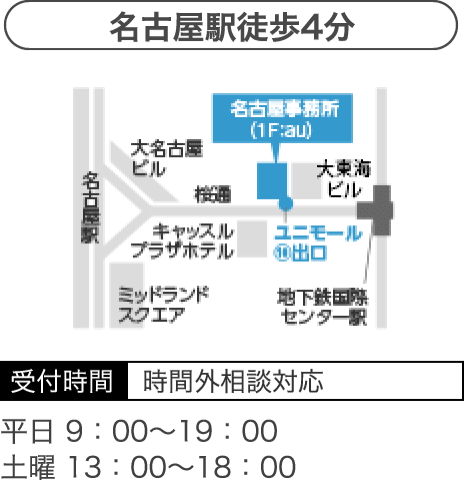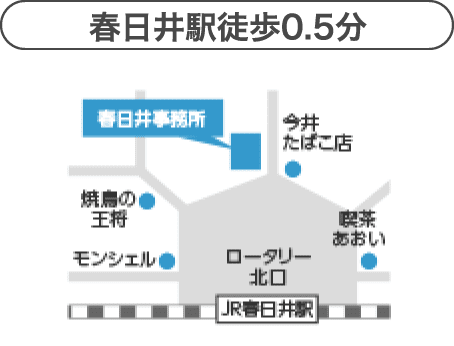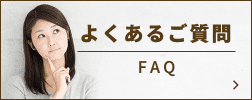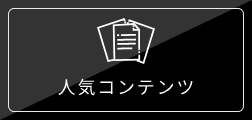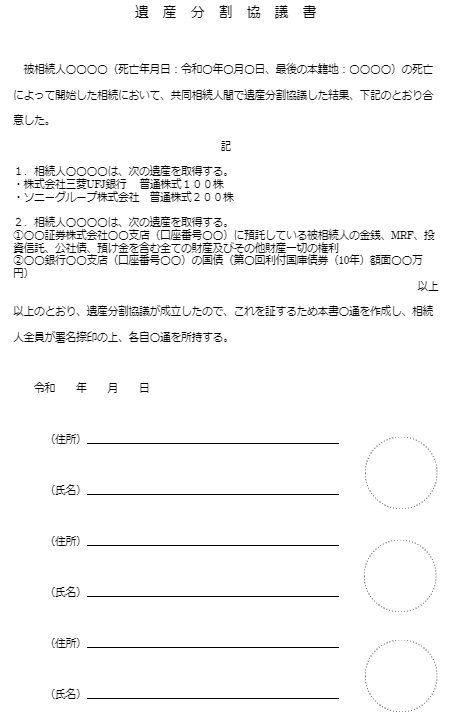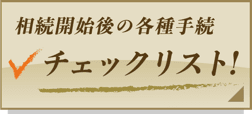目次
回答
遺留分侵害額請求権とは、遺留分侵害額請求によって生じた金銭債権、すなわち遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利のことをいいます。
遺留分制度の民法改正により、主に次の点が変わりました。
①権利の金銭債権化
②遺留分の対象となる、相続人に対する生前贈与の時期を、相続開始前10年間に限定
③遺留分の対象となる、相続人に対する贈与の範囲を限定
なお、遺留分権利者、遺留分の割合、遺留分侵害額請求権の意思表示の期限等については、改正によっても変更はありません。
新しい遺留分制度は、改正法の施行日である令和元年7月1日以降に開始した相続について適用されます。それよりも前に開始した相続については、遺留分請求が施行日以降であったとしても、改正前の遺留分制度が適用されます。
解説
1.遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、遺留分侵害額請求によって生じた金銭債権のことをいいます。
民法改正前の遺留分制度は、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分減殺請求の対象となった目的物の所有権(共有持分権)が遺留分権利者に戻ることとなり、当然に共有関係となるものでした。
しかし、例えば遺留分を侵害した贈与や遺贈の目的物が不動産の場合、当然に不動産が贈与や遺贈を受けた者と遺留分権利者との共有状態となり、当該不動産が会社の事業用不動産であるような場合に、その処分等に支障が生じるケースがありました。
同様に、遺留分を侵害した贈与や遺贈の目的物が株式である場合には、事業承継に関して後継者とそうでない者が株を分け合うこととなり、会社の事業承継や経営上問題となることがありました。
このような場合、改正前の遺留分制度においては、遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使しても、贈与や遺贈を受けた者に対し、金銭での支払を請求することはできず、減殺請求を受けた相手方が金銭での弁償を選択できるにすぎませんでした。
その結果、相手方が金銭での支払いを選択しなかった場合、不動産の共有物分割に関する紛争が生じる等の問題がありました。
そこで改正法は、遺留分侵害額請求権の行使から生じる権利を金銭債権(遺留分侵害額をお金で払ってもらうことのできる権利)としました。その結果、遺留分侵害額請求権の行使によって、目的物が当然に共有状態となることはなくなりました。
2.改正によって変わった点
遺留分制度の改正によって変わった主な点をまとめると、次のとおりとなります。
2-1.遺留分侵害額請求権の行使から生じる権利が金銭債権となった
前述のとおり、遺留分侵害額請求権の行使から生じる権利は、金銭債権(遺留分侵害額をお金で払ってもらうことのできる権利)となりました。
この権利は形成権とされ、一旦行使した後は、債権の消滅時効に関する規定が適用されます(民法166条)。
また、遺留分侵害額請求権の行使の時が履行期であるため、その翌日から遅延損害金が発生します。
そこで、遺留分侵害額に相当する金銭をすぐに準備できない被請求者(請求を受けた者)のため、申立により、裁判所が金銭債務の全部又は一部の支払いについて相当の期限を付与することができるものとされています。
2-2.相続人に対する生前贈与の時期を10年間に限定
改正前の遺留分制度では、相続人に対する生前贈与について、その時期の制限なく、遺留分の対象となる財産に含まれていました。
しかし、改正法では、相続人に対する生前贈与の時期について、相続開始の10年以内になされたものに限定されました。
そのため、相続開始の10年よりも前に贈与された財産については、遺留分算定の基礎財産に含めなくてもよくなりました。
次の表は、生前贈与について、遺留分の対象となる財産の範囲を整理したものです。なお、遺贈は全て遺留分の対象となる財産に含まれます。
|
生前贈与の受贈者 |
贈与の時期 |
遺留分の対象となるか |
|
相続人以外 |
相続開始の1年以内 |
すべて対象となる |
|
相続人以外 |
相続開始の1年より以前 |
贈与者・受贈者ともに遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときのみ、対象となる(民法1044条1項) |
|
相続人 |
相続開始日が2019.6.30以前⇒限定なし |
当該贈与が特別受益にあたる場合は、原則として対象となる(最高裁判所第三小法廷平成10年3月24日判決) |
|
相続開始日が2019.7.1以降⇒相続開始の10年以内に限定 |
||
|
相続人 |
相続開始の10年前よりも前の日 |
贈与者・受贈者ともに遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときのみ、対象となる(民法1044条3項) |
2-3.相続人に対する贈与の範囲を限定
改正後の遺留分制度では、相続人に対する贈与について、相続開始1年以内のものについても、「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る」として、遺留分算定の基礎となる財産の価額に含まれる贈与を限定しました。
したがって、改正後の遺留分制度では、遺留分算定の基礎となる財産の価額は、次の式で算出されることになります。
遺留分算定の基礎となる財産の価額=「相続開始時の財産(プラスの財産)」の価額」+「相続人以外の第三者に相続開始前1年間にした贈与財産の価額」+「相続人に対する相続開始前10年間の婚姻若しくは養子縁組又は生計の資本としての贈与の価額」-「相続債務の価額」
3.変わらない点
3-1.遺留分権利者
遺留分権利者については、改正前と変更はありません。すなわち、以下のとおり、遺留分権利者及びその承継人となります。
-
遺留分権利者
・配偶者
・子(子が既に死亡している場合は、子の代襲相続人)
・直系尊属(父母、父母が既に死亡している場合は祖父母等)
・胎児(生きて生まれた場合は、子として扱います)
-
遺留分権利者の承継人
・遺留分権利者の相続人
・遺留分権利者の包括受遺者
・遺留分権利者から相続分の譲渡を受けた人
・遺留分権利者からの特定承継人
3-2.遺留分の割合
遺留分の割合についても、改正による変更はありません。遺留分の割合は、次の表のとおりです。
|
相続人 |
遺留分の割合 |
|
①父母など直系尊属のみの場合 |
相続財産の3分の1×法定相続分 |
|
②それ以外全ての場合 ア 子供など直系卑属のみの場合 イ 子供など直系卑属と配偶者の場合 ウ 父母など直系尊属と配偶者の場合 エ 配偶者のみの場合 |
相続財産の2分の1×法定相続分 |
3-3.遺留分侵害額請求権の期限(意思表示の期限)
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年で時効によって消滅します(民法1048条前段)。そして相続開始から10年経過すれば、知ったかどうかを問わず、権利を失います(除斥期間、民法1048条後段)。
4.改正法の適用時期
遺留分制度の民法改正は、令和元年7月1日に施行されますが、施行日前に開始した相続については、改正前の制度が適用されます。
すなわち、被相続人の死亡日が令和元年7月1日より前(令和元年6月30日まで)であれば、改正前の遺留分制度が適用されます。例えば、被相続人が令和元年6月30日に死亡し、令和元年10月1日に遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使した場合、改正前の遺留分制度が適用されます。
一方、被相続人の死亡日が令和元年7月1日以降であれば、改正後の遺留分制度が適用されることになります。
参考条文
民法
1044条
1 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。