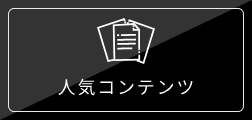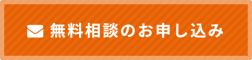遺言のよくあるご質問一覧
成年被後見人が遺言を作成することはできますか?
成年被後見人も、満15歳に達しており、かつ遺言能力を有していれば、有効に遺言を作成することができます。作成する遺言の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言等)についても、制限はありません。もっとも、成年被後見人は、事理を弁識する能力を欠く常況にある者であるため、有効に遺言を作成するためには、上記に加え、...
詳しくはこちら
自筆証書遺言のメリット・デメリットは何でしょうか?
自筆証書遺言は、作成に費用がかからず、手軽に作成できる等のメリットがある一方、法律に定められた方法によって作成されていないと無効となってしまうリスク、偽造や変造・隠匿の恐れがある等のデメリットがあります。
1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、簡単に言うと、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上...
詳しくはこちら
遺言書が2通見つかりました。この場合、どちらが有効なのでしょうか?
遺言書が2通(複数)ある場合について、民法は、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定しています(民法1023条1項)。したがって、2通の遺言書の内容が抵触する場合、作成日の新しい遺言が有効となります。もっとも、これは、「抵触する...
詳しくはこちら
特に遺言を遺したほうがよい場合はありますか
遺言を遺すかどうかは、自由です。
しかし遺言がない場合、被相続人の遺産は、民法の規定する法定相続分にしたがって承継されます。一般的には、以下のようなケースにおいては、遺言を遺す必要性が高いように思われます。
①夫婦間に子供がいない場合
②再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
③長男の配偶者に財産を分け...
詳しくはこちら
遺言事項とは何でしょうか。遺言事項以外のことを遺言に書いた場合、無効でしょうか。
遺言事項とは、遺言書に記載することで法的な効力を有する事項のことをいいます。
遺言事項は、民法その他の法律で法定されており、相続や財産に関する事項(相続分の指定や遺産分割方法の指定など)、身分に関する事項(認知や未成年後見人の指定など)、遺言の執行に関する事項(遺言執行者の指定など)、そ...
詳しくはこちら
遺言者の死亡以前に受遺者(財産をもらう人)が死亡していた場合、遺言(遺贈)の効力はどうなりますか
遺言は原則として、遺言者が死亡したときからその効力を生じます。そのため、遺言者の死亡以前に受遺者(財産をもらう人)が死亡していた場合は、遺言は当該部分について、無効となります。
そして、受遺者が取得する予定であった財産は、相続財産として、法定相続人が法定相続分で承継することになります。ただし、遺...
詳しくはこちら
遺言執行者の権限等は、民法改正によってどのように変わりましたか(令和元年7月施行)
回答
民法改正により、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するものとされました(民法1012条1項)。
民法改正前は、遺言執行者は相続人の代理人とみなされていたことより、遺言執行者の法的地位が不明確でしたが、改正によって遺言者の意思...
詳しくはこちら
自筆証書遺言に関する民法改正内容、遺言書保管制度について教えてください(平成31年1月、令和2年7月施行)
回答
自筆証書遺言に関する民法改正により、遺言者は、自筆証書遺言の財産目録部分について、パソコンで作成した目録や不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、通帳の写し等を添付することができるようになります。
その場合、遺言者は、財産目録の各ページ(自書によらない記載がその両面にある場合は、その両面)に...
詳しくはこちら
遺言執行者に指定されたのですが、断ることはできますか
遺言執行者に指定されたとしても、遺言執行者に就任するかどうかは、自由に決めることができます。なぜなら、遺言の執行には専門知識を要することも多いため、遺言の内容によっては遺言執行者に多大な負担となることもあり、また、遺言等によって一方的に指定を受けた場合にその就任を強制することはできないためです。
...
詳しくはこちら
公正証書遺言のメリット・デメリットは何でしょうか
回答
公正証書遺言は、公証人が遺言者に遺言内容を確認し、その内容を公正証書として作成する遺言です。
公証人は、裁判官や検察官などの法律実務の経験が豊富で、正確な法律知識に基づいて公正証書遺言を作成するため、公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
・家庭裁判所での検認手続が不要である(...
詳しくはこちら
遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。